大学の授業で扱っていたのだが、なんとなく読み返したくなって購入、再読した。藤田正勝先生の解説がついており、さらにわかりやすくなっている。
どうしてこれを読み返したいのか、読み始めた当初はわからなかった。ただ「いき」って何だろう?と改めて思ったわけではないことは確かだった。
今回の読書で一番大事だったのは、本題に入る前の「序」にあった「生きた哲学は現実を理解し得るものでなくてはならぬ。」であった。また、この本は著者がヨーロッパに滞在しているときに書かれたようである……というのも、日本でいうところの「いき」に替わることばがヨーロッパになく、その概念や、成立するにあたっての経緯や背景について、思索していくことになっている。こうして「いき」の構造について掘り下げ、他の言葉との差異を見出すわけだが、このプロセス自体にぴんときたわけである。
今関わっているしごとの案件や趣味の領域で「もうちょっとこのことを知りたい」と思ったり「それは結局どういうことなんだろう?」と思うことがある。いずれにしても「対象の世界を掘り下げたいな」という欲求はおなじだ。その欲求および求めていくプロセスというのが、「生きた哲学」につながっていくように思うし、なんだか古代の哲学にもそんなような一説があった記憶がある。そこを明瞭な日本語として構成的に言語化していくだけの能力は持ち合わせていないが、ばくぜんとこれまで関心をもった世界のことはきちんとまとめるというか、ひとつの形にしたいという思いはあり、そのためにも引き続き、追求していくことと、いよいよ客観的な視点から掘り下げていったような内容を書く練習をしていけるとよいのかもしれない。
読んでくださり、ありがとうございます。なんで読みたいか思い出せたのでなんだかすっきり。
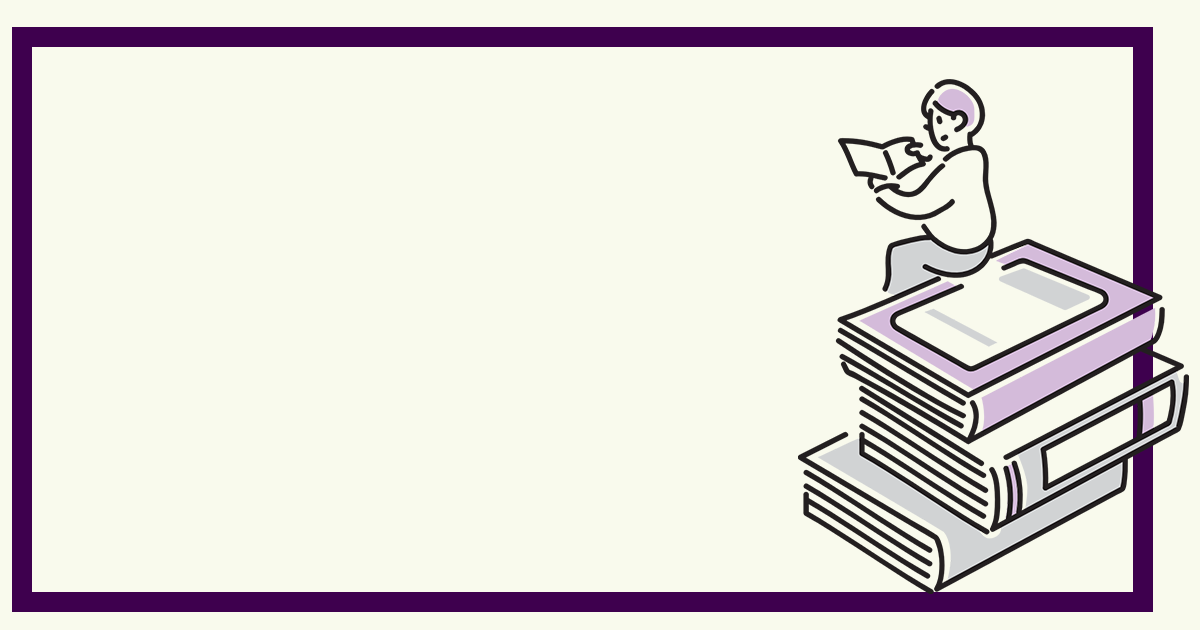

コメント