サークルの同志である詩音氏と竹雀氏いちおしの作品。すすめられたのはかれこれ、去年の秋頃だった気がする……。
海と山に囲まれた閉鎖空間のなかで生きる複雑な血族の物語という、だいぶ入り組んだテーマなので、さくさくは進まず、読み終えるまでに一ヶ月かかった。まず家系図が複雑すぎる。家族の名前も似ていて、覚えるまで一苦労だ。
主人公・秋幸はきょうだいのなかでただ一人実母に連れられ、育ての親の姓で生きている。血縁に憎悪をおぼえる一方で、土方として働いているときの、自然と一体化する瞬間をこよなく愛している。本編ではこのエピソードが何度も繰り返して描かれる。幾度となく出てくる光と風は、秋幸という個別の人間を吸収し、彼を「なにものでもない者」にしてくれる。彼が血縁の呪いから解放される唯一の時間だ。このシーンの描写がわたしはとてもすきだった。なんだか、読んでいてきもちよかった。
自らのルーツの不安定さがひとの不安定さをよびおこすというのは、今でもある。ただ、この作品が書かれた時代は現代のように少子化も核家族化もしていないため身内がきわめて近いところに住んでいる。それぞれの内に潜む感情や経験のズレが今よりも目に見えやすく、それによる衝突や軋轢もそうとうダイレクトに生じていたように思う。このような状況というのは当時、『枯木灘』ほど複雑ではないにせよ、現実にもじゅうぶんにありえたのではないか。小説のかたちを取りながらもどこか現実味をおびたエピソードなのではないかと感じる。
もうひとつ特徴的なのはこの作品が大きな物語の展開をもたない、ということだ。最後にひとつだけ事件が起こるが、それまでは淡々と日常を繰り返し、ときに過去の回想をしては今に戻り、自分の存在について考える。さきほど自然と一体化するシーンが繰り返し描かれていると書いたが、この「繰り返し」というのが非常によく効いていて、カノン的だなーと感じた。カノン的というのは「パッヘルベルのカノン」に代表される、同じ旋律が時間をずらして演奏され、重なっていくことで深みを増していく、という意味で用いている。これが『枯木灘』を読んでいて一番感じたところだった。繰り返される日常、しかし、それらが重なっていく中で秋幸の血への憎悪は膨らみ、終盤に起こる事件として結実する。一回的なできごとがそうさせたのではなく、丁重にエピソードが重なり重なり……クライマックスがやってくる。しかも繰り返しを描いているにもかかわらず飽きさせない。ここに著者・中上健次の手腕があるのだと思う。
読み終えたあとで知ったのだが、これは三部作の最後の一冊らしい。前半のふたつも興味はあるので読んでみたいきもちはあるが、ちょっと本を積んでいるので崩してから再考する。
今日も読んでくださり、ありがとうございます。読んだのがだいぶ前で記憶がスカスカしてしまった……やったらすぐ書かないとだめですね。

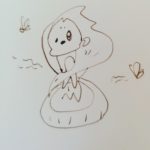
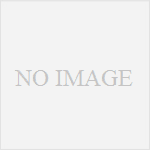
コメント