歯をみがいているとき、鏡の隅に貼られたシールが目にとまった。どうやら鏡のそうじの仕方が書いてあるようだ。
「5倍に薄めた無色透明の中性洗剤をやわらかいハンドタオルにつけて拭いてください」とある。我が家の洗剤は中性かつ無色透明なので、鏡のそうじに使えそうである。ずっと新聞紙で鏡をそうじしていたので、今度ためしてみよう。口をゆすいで歯ぶらしを拭き、定位置に戻す。
それから日記を書いていると、万年筆のインクが切れた。万年筆は書き心地よく、すっかりよい相棒となっているのだが、毎日それなりの記録をしているとすぐにインクがなくなる。小瓶に水を貯め、ペン先を外して浸す。無色透明の水に、青いインクが糸のように広がって溶けだす。水はだんだん無色ではなくなって、翌朝にはすっかり青い。わたしはこの光景がすきだった。広い水槽のなかでくらげがただよっているように見えて、うっとりしてしまう。やわらかな青い糸がじょじょに溶けだすのを見ると、死ぬときはこういうふうに消えてなくなりたいと思う。
考えてみると、無色というのはふしぎなものだ。無色透明ということば以外で、まずお目にかからない。かりに無色不透明といわれたら、きっとわたしたちの多くは白を想像する。しかし白は白という有色で、無色ではない。光あるこの世界のなかで、まったく無色のものというのはきっと、そんなに多くはない。それだからつかみどころがなくて、なにか神秘的な予感がする。
また透明としかつながることのできない無色の繊細さを、たいへんに孤高なもののように感じる。そのまじりけのなさは、どこか素数と似ている。1とその数でしか割れない孤独な数字、一方で無色は透明としかつながれない孤独な色、相似形だ。色に番号がついているなら、きっと無色は素数だと思う。はじめ、無色ならゼロだろうと考えたが、ゼロと透明はむすびついたらゼロになりそうで、透明でも不透明でもないなにかの存在を連想してしまって、もはやこの世で経験した色を想像することができなかった。
今日も読んでくださり、ありがとうございます。だいたいこういうのは考え出すと袋小路に入るのですが、おもしろいのよね。
◆無色という色

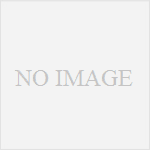
コメント