きっかけは定かではないが、旅行をしたり、展示を見にいったりして、その土地のおみやげや住んでいた人々の風土記というか、生活を見るのがたのしい。これまでも関心がないではなかったが、積極的に意識を向けるようになったのは、大阪の民族学博物館にいってみたことが大きいのかな。さらにここ最近は現地の民藝品を時々買うなどするようになった。物を極力減らし減らし生きていた大学時代を考えると驚くべき変化である。
具体的にはアフリカの、なんともいえないシュールな表情をしたチータ?虎?のおきものや、大好きな福岡の伝統工芸「うそ」(厄を食べてくれる→しあわせをもってくる鳥らしい)、そしてこけしである。こけしについては、目黒にある雅叙園・百段階段のワンフロアに、古今東西の(とはいえこけしが主に作られていたのは東北地方なのだが)こけしが会していたことがあり、そうとうな情報量で全てを記憶することは到底できなかったが、その中でのっぺらぼうのものを猛烈に気に入ってしまった。首がふりふり動き、回るそれは、岩手・盛岡で主につくられている「キナキナ」というものだ。木目がそのまま作品にでてくるので、木の種類によっても表情がかわるのがおもしろい。
その他アート作品で小さなものを購入したり、BPL(遊んでいる音楽ゲームのプロリーグ)選手のアクスタなどをかざっているうちに、少し机の一角がにぎやかになってきており、古今東西の文化が雑多に置かれた不思議な空間を形成している。次の旅はしばらく先だが、これまで見過ごしていたところを関心をもってみられるようになるのは、あみのめがこまかくなるようで楽しいな。
読んでくださり、ありがとうございます。工人さんが減ってきているというので、いつかまぼろしの作品になってしまうかもしれないのですなー。

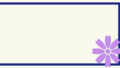

コメント