7月上旬に体験したアラビア書道がすこぶる楽しく、2回目に参加してきた。本利用になると書道に必要なツールを買わせてもらえるので、家でも練習ができると思い、間をあけず行きたかったのだ。
初回、見本をみながらアラビア数字(よくいうアラビア数字ではなく、アラビア文字の数字がある)を書く時間が10分ほどあった。実はここ半年くらい、iPhoneのロック画面の時計の文字を変えていて、というのも、うっかり落として悪意ある人に拾われても、一瞬なぞの文字だと怯んでくれるかなといった、淡い期待からだったのだが、それがアラビア文字だったのである。自分も読めないし、そもそも文字自体がなんだかわかっていないのに設定しているというのが、味わいぶかいところであるが、それは置いておこう。
毎日目にするうちに、起床・就寝時間である5,6,7と11,12あたりは読めるようになってきていたが、他の数字はよくわからないままであったので、「え、これアラビア文字だったんだ」と拍子抜けした。ここで出会えるとは。3周くらい書いてみて、難しさにほどよい歯応えを感じていたところ、「あまり数字ばっかりでもつまらないので、アルファベットをやってみましょうか」と先生から声をかけられ、やや、後ろ髪をひかれるように移行したのであった。
翌朝、普段通り起きてみると、あれだけ謎の数字だったアラビア数字がすっかり解読できているではないか。たかだか3周書いただけで、だ。詰まっていたパズルが解けたような感覚だった。思い返せば、小学生の頃は漢字の書き取り欄が教本にあった。当時は「やりなさい」といわんばかりにマスがあいているので漫然と埋めていったが、あれには確かに意味があったのだ。同じ動きを続けることはそんなにつらくなかったのと、書くことはおもしろかったので、今でもまあまあ漢字はパッと出てくれて、助かっている。
スマートフォンやデジタル化の勢いは著しく、手書きでわざわざ取り組む機会はつくりにいかないと掴めないような時代であるが、自分の手でひたすらやってみることの価値が相対的に浮き彫りになっているのかもしれない。これは、自分にとっては韓国語がいい例で、DropsとDuolingoというアプリだけで文字や単語、言い回しを習得してきた。街中やSNSで韓国語をみたとき、断片的に理解することはできても、文章の流れとして理解するのはむずかしく、アウトプットにおいても、単語を作るのにも時間がかかる。向き不向きもあるのかもしれないが、もしかすると、デジタルでの実践は実況動画をみているだけのような状態なのかもしれない。
読んでくださり、ありがとうございます。ゲームも結局自分がやったほうがうまくなりますし実感もわきますものね。この「実感」の感覚はもう少し丁寧に掘り下げてあげられると、何か新しいことをするのにも取り組みやすくなるような気がするな。

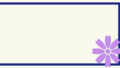

コメント