読もうと思っていたきっかけはなんだったか、忘れてしまったのだが『ふがいない僕は空を見た』(窪美澄)などとセットで買っていたので、人の愛欲や性、生きる苦しみみたいなのを摂取したかったのかなと思う。
クッツェーの作品はこれが初めてで、まずおどろいたのが文章のしなやかさ。原文で読んでいるわけではないので、訳がよいのかもしれないが、物語の痛みや重みに対して、ひどくスムースに読み進められる。そのギャップがさらに物語を深刻にしているような気もする。
物語の舞台は、アパルトヘイト廃止以降の南アフリカということで、まだ人種間のわだかまりは残っていることが予測される。主人公は52歳の大学教授で、軽い気持ちで手を出した女学生とのスキャンダルでケープタウンの大学を追われ、東ケープのセーレムという片田舎にいる娘の元に転がり込むこととなる。そこで相入れない価値観や文化、そして事件に巻き込まれた主人公は、そこでの生活を通して、きわめてゆっくりと変化していく。その間の思いの頑なさや、それを解いていくまでの過程、まわりのひとびとと、語るものには事欠かない。ちいさなセクションに区切られて話は進むのだが、1つ1つのセクションで何かが起きている。毎回雷が落ちるみたいな感じだった。
メインとなる、考え方や文化様式の異なるセーレムになじめない主人公(彼)と、そこに留まってうまくやっていこうとする娘・ルーシーのぶつかりあいは、再開を喜んだ初期の頃と、ほとんど断絶しそうになってしまう終盤の対比がせつない。人は親子であろうと独立したひとりの人間であり、相入れないときには相入れないのだと痛感する。ある事件が起こり、そこから何かが大きく変化するのかといえば、すぐには変化しない。横行する強盗やレイプ、半ば静観する警察機関、村の有力者、こんなところに止まるべきではないと身を娘の案じる彼と、それをはねのけ、土地に留まろうとするルーシーとの、おのれの正しさを両者一歩も譲らず、かたくなに進んでいく道中には緊張感がある。本当に後半の方に入ってくると、彼はセーレムの人々への接し方がほんの少しだけやわらぐ。一度ケープタウンに戻ったり、離婚した妻に会ったりと、変化のきっかけはあるのだが、結局はセーレムへ戻って過ごすようになる。
当初、タイトルである『恥辱』は、主人公のスキャンダルそのものから転落していく人生のことを指していると思っていた。実際、スキャンダルがあって彼は大学教授の身分を失い、身も心もやつれていくのだが、読んでいくうちに、それだけではないなと感じられてくる。中世の詩の素養がないのでバイロンやダンテの引用部分についてしっかりと理解しているわけではないが、後半はとくに、その愛の描写がどっと増え、現実の彼の生活と創作とが混在し、極限状態のの人間の認識と甘美な想像の世界がとろけ、不思議な時間が形成される。これだけずっと、事件とすれ違いと失望が続く中、彼を救ったもののひとつが文学であった。彼のオペラがいったん結実をすると、物語も佳境に向かっていく。その締めくくりはこれまでの絶望と地続きではありながらも、か細い光がみてとれる。救いなのかもしれない。
ずーっと展開していくので飽きずに読み進めてしまった。自らと異なる世界に放られたとき、人がそれを受け入れるまでの過程と、決して良好とはいえない環境だとしても、行くべき方向を見出して生きていこうとする人間のたくましさを感じる作品だった。そう、たくましかった。登場人物の誰もが。
読んでくださり、ありがとうございます。他の作品も読んでみようかと思います。
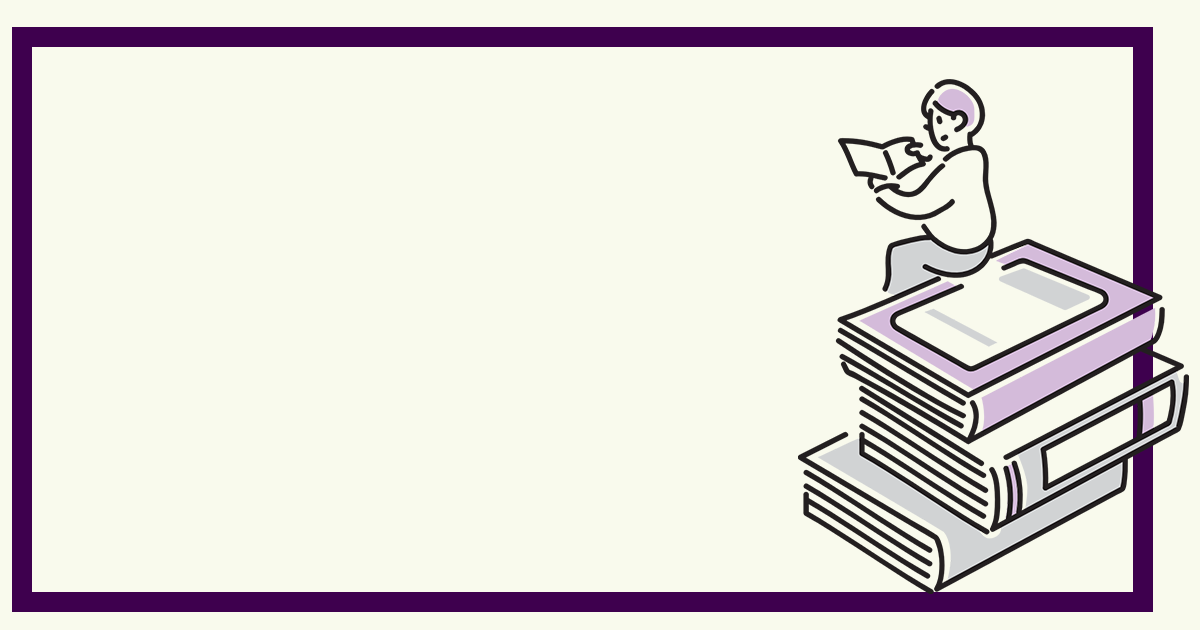

コメント