今年の頭に加入した、大阪の国立民族学博物館・友の会で案内のあった「不安の時代」という講演を聞いてきた。平日夜に大阪に行くことはむずかしいのでリモートだが、4人のパネリストが講演をして、後半はディスカッションという形だったのが、ひじょうに面白かった。
くわしい内容は割愛するが、大きく分けて①20世紀前半の東京(精神疾患にまつわる歴史を患者側からアプローチしていた)②社会格差が引き起こすブラジル③神秘主義集団をベース としたセネガルの若者のありかた④韓国の若者の鬱火(ちょっとこれは日本のいわゆる鬱とは違い、怒りの感情も伴った病態だという)の4テーマだった。とくに、日本の若者の不安とありかたが異なっているな〜というのをブラジルとセネガルは感じた。そもそも宗教的な背景があったのが瓦解していくことで不安定になった側面をもつブラジルと、逆に不安定な状況でありながら神秘主義集団リーダーを推し、政治的な影響を及ぼしていくことで進んでいこうとするセネガルの対比がおもしろかった。また、ふたつめ、みっつめの講演については、宗教だけでなく不安の要因として国家・コミュニティ(家族、宗教)・経済といった大きな要素にもふれ、全体からテーマとなる国についてお話をされており、環境的・歴史的背景も日本と異なることが強調されており、わかりやすかった。
一方、日本の講演は20世紀前半、戦前日本の精神病患者について。かつては精神病院が居住地区のそばにあり、今のように山奥に構えている時代ではなかった。いまだに日本は精神病院の病床数が世界一位という不名誉な状況にあり、生活環境に患者を受け入れるということについては時代を逆行しているところがある。そういった状況もあり、精神的な不安をあおりやすい側面もあるのかなーとちょっとだけ思った。
韓国の事例は、アメリカのDSM-Ⅴ(一般的に精神疾患の診断に用いるガイドライン)には記載されていないが、東洋医学的には「鬱火」という病態はみとめられているという。日本と異なり「怒りの発露がある」というのは特徴的である。一方で、怒りの発露が政治体制に向かいやすい傾向について、たしかにそういったイメージはあったものの、その要因のひとつとして、人々が「政治がやってくれる」とやや人任せな面があるのではないかと講演者の先生はおっしゃっていた。お名前からみて韓国の方かなという気はするので、肌感覚もあってのお話なのかなという気がした。
個人的に印象に残ったのは、宗教が人びとをまとめ、安心をもたらす効能をもつということだ。日本にいて無宗教で過ごしていると、この感覚はピンときづらいが、セネガルの例で、自身の信仰する神秘主義の指導者を「推し」、選挙等で政治の場で活躍してもらうといった、国のありかたまでも影響するのをみると、すごいなーと思った。それだけ、人が生きる指針として委ねる先になるのかもしれない。一方で、そういった地盤の弱い日本でオウム真理教的なカルトが当時、若者の期待の先となったことも納得がいってしまった。
話は逸れるが、ICFが発表している「健康」は今のところ、「完全に、身体、精神、社会、霊的によい動的な状態である」と定義されている。日本では「霊的」「動的な状態」の2つは採択されていないが、霊的というのがスピリチュアル的なもの、たとえば宗教であったり自然の中で感じる癒しなどがそれにあたるようだ。動的な状態というのは今回の話とは関わらないが、単に健康な状態だからいいよね!ということではなく、健康であることを資源として、やっていきましょう、といったテイストらしい。ここでいいたいのは、ブラジルでは無宗教の人がふえていくことによってスピリチュアル的なところの安寧や基盤を失ったことで不安が増大している側面があり(もちろんそれがすべてではない)、逆にセネガルではその基盤が作用していることで、不安定な情勢に対抗できているようにも解釈できる
不安のあり方や行方について国と個人個人が働きかけていくことで、不安定な動向を防ぐことができるように考えられるが、それぞれの国によってその様相が大きく異なることが学びになった。ついつい自分のいるフィールドを基準としてものを考えてしまうものだが、つどつど想定される他者の背景を捉え直すことで、ものごとの理解もすすむようにおもえた。


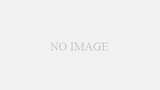
コメント