9月に成年後見研修の後半が始まり、土日がちょっと窮屈になりつつあり、しごとも大きく変わらずではあるが、怒りのパワーで平日の夜にちょっと気になる講座を受けるようになった(用事を先に入れれば、「先約があるので」とゴリ押せるという労働Tips)。前回の記事で、行政書士会のオリエンテーションに参加してみたこともあり、少し顔見知りの方もでき、あいさつがしやすくなった。だからといって深い話ができるわけではないが、いつまでたっても孤軍奮闘というのはエネルギーを消耗するので、ちょっとでも安心できる要素があると違う。今回は相続と税務の勉強会への参加と、有志で行われている勉強会の見学をしてきた。
これまでは知らない世界に入っていくとき、それなりに緊張感を伴っていたが、会社や、力のある他人の後ろ盾があるのと違って、ひとりで歩み入るのはその比にならないほどひきしまる。しごと関連であれば、生活に直結するのでなおさらである。そういった緊張感をもって事に臨む経験もなんだか新鮮だった。つかれたけど。とはいえ、コミュニティにいる人たちの意識の仕方や視点の傾向などを垣間見ることができ、今のしごととの違いも感じるところであった。
相続業務の大変さとポイントを端的に知ることができたことはよかった。実際やってみるかどうかはちょっと悩むが、人の生と死は不可避で、その後のことというのは普通1,2回くらいしか立ち会うことがないので、もっと知ってみてもよいのかもしれない。
実務について話を聞くようになって、大きく変わったなと思うのが、普段行くお店などで「どういうタイミングで役に立てるんだろう」というのを考えるようになり、なじみのお店では許可のことを聞いてみたりと、アクセスポイントが増えた。
実現にむけて動くのには緊張や不安もあるが、いっぽうで、新奇性のあるものにワクワクしている。あらたな世界に足を踏み入れていくなかで、今の職場と同じく、なり手の少なさは成年後見においてはさけばれているようで、そう今のしごとと変わらない混沌がひそんでいるような香りがした。そこで与え、手に入るものは何になるんだろう。
読んでくださり、ありがとうございます。人が少ないということは、救う先も限られるということです。その、リソースをどこに注ぐんだろう、そして、それはどうやって決めるんだろう、ということが気になっています。
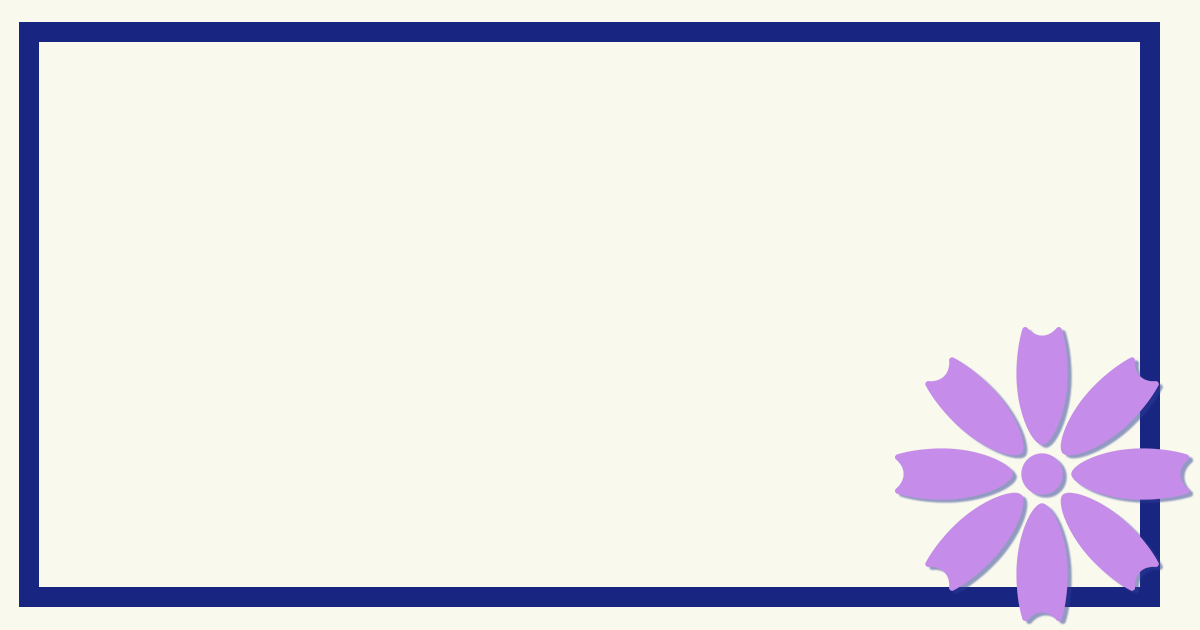


コメント