うだうだしていたが、ようやっと辞める話ができた。話ができたというのは、受理されたというのとは少し違う。わずかな人数で構成される零細企業であること、会社設立からいたので知っていることが多く、ちょっと、このあとどういった話し合いになるかはわからないが、まぁ、会社でしごとを進めるにあたって障壁になることが予想されることとしては、仕事がだいぶ属人化しているのでそれを解き放つことと、そもそもの人間の数が足りていないことだ。
ふたつの大きな問題のうち、属人化されている仕事は徐々に誰でもできるような流れへとすきまの時間で動いていたのでよいとして、人足についてはどうしようもない。とはいえ、自分のせいで人が増えなかったわけではなく、人事の問題なので、あまり気にしなくてもいいのかな。聞くと、個人と組織を結びつけすぎることで、辞めづらくしてくることはよくあるような感じと聞くところもあり、自分の会社でもそういった伝え方をしている場面をみたので、まぁ、そんなものなのかなと思う。そう考えると、さっさとAIができる部分を代替してくれた方が、組織としてもめんどくさくないのかもしれない。
さらっと書いてはいるものの、自分で決めてさっと行動に移したわけではない。一定の環境の中にいると価値観が偏るというのは誰にでもあって、自分の会社にいる時間が一週間の中で多ければ、とうぜんその風土に染まりやすくなる。よそから因習村にやってきたキャラクターたちがおかしくなっていくのはそういうわけである。
では、どうそこを突破したのかといえば、普段会わない人たちから生き方の話を聞き、風土を一色にしないことであった。友人でもいいし、よく行くお店のマスターでもいいし、それなりに紆余曲折をへてきた人を知っていれば、その人だっていいと思う。いろいろな、もしくは響くような生き方があれば最高だが、それを聞いて、自分が会社を辞める・辞めないという事柄がいい意味で矮小化され、その後のことを考えやすくなる。自分の意思と、そういった話を胸にして臨むと、ふしぎと何か強く言われても、あまり響かなくなる。自分と会社との一致度とでもいうのか、その度合いが下がっているので、なんだか辞めるって言ってるなー、引き止めてるなーと、第三者的な目線でものをみやすい。
ロボットアニメの中には、そのロボットとのシンクロ度が上がると強くなるというのがあるが、職場を離れるときというのはその逆なんだと気づく。アニメと違うのは、パイロットの唯一性こそが強さと結びつく展開が多い中、会社は組織なので、代替可能で、いかようにも代謝していける設計をしておいたほうが強くなるということで、それはどちらかというと悪役側の名もないキャラクターにあてられる役割なんだよな。そんなことを考えていたら、主人公陣営は組織というより個人、悪役側は組織として描写されることが多いなーという気づきが。そういう意味では、個に偏りすぎているのが弊社だったのかなと思うし、その良さもある一方、欠員のダメージへのリスクマネジメントが甘かったという見方もできるだろう。
読んでくださり、ありがとうございます。悪役側のマネジメントすごい!みたいな考察読むのおもしろいですよね。
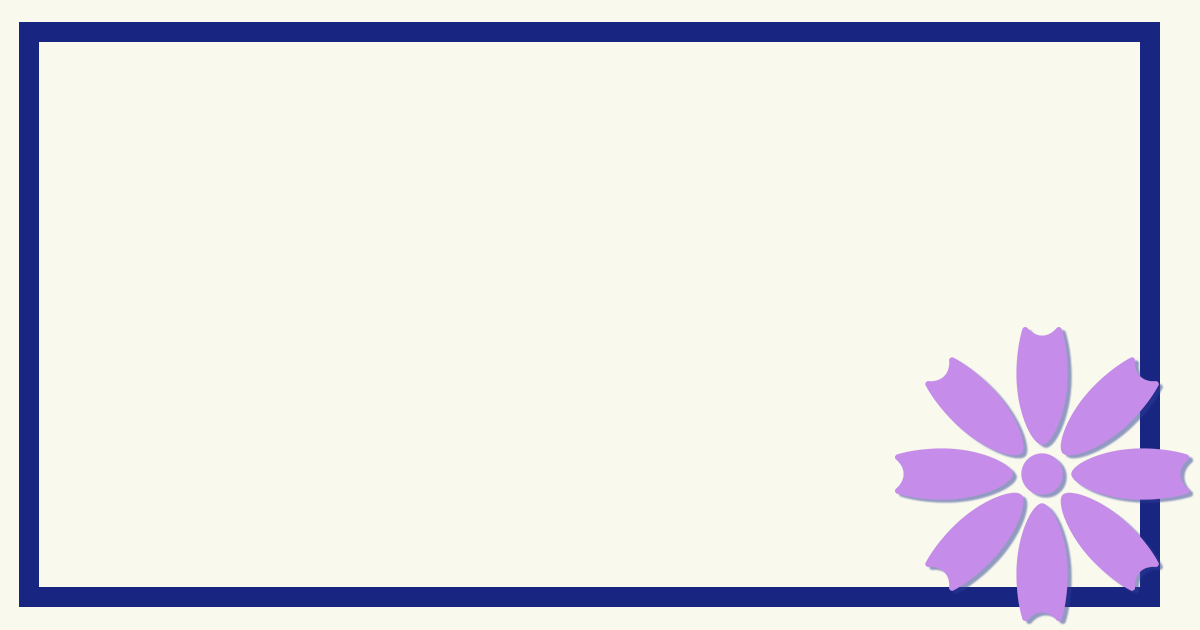

コメント