読書、これはノンフィクションでもフィクションでもかまわないのだが「あ、これだ」と名探偵コナンのごとき(視聴していたのが十年以上前なので、最近のお話でこの描写はもうないかもしれない)閃きのカットインが入るような瞬間がある。何か日常や仕事の中でもやもやとしていたことや、何か考えていたがまとまらないまま消えてしまったことが、読書の中でつながったり、ふと思い出されて「こういうことだったんだ」とストンと落ちるのだ。「文学の中で思考を整理する」などというとしゃれた感じもするが、その実しみじみと素朴で、なんか読んでたら落ちてきましたくらいのものである。
最近だと『異常論文』のあとがきにあった、論文と小説の違いを自己の外に向かうか内に向かうかという違いがある、というのをみて「たしかにまぁ、いわれてみればそうか」という納得感を抱いたまま、『李陵・山月記』より『李陵』から、司馬遷の歴史の描写に対する考え方に出会う。孔子のいう「而述不作」、もともとは先人の教えや解釈を引き継ぎ、それに基づいて学問を進めることを示すのだが、転じて、事実を述べて主観を交えないという文脈でも使われることがあったとのことだ。
少し論点は異なるが、なんだかちょっと似ているなーと脳内カットインが入る。げんみつには、司馬遷は歴史書の著者なので論文かどうかは怪しい部分があるのだが、とはいえ「論文/小説」と「述ベル/書ク」といった記載には通ずるものを感じてしまった。その後司馬遷は、自身のつくった項羽と虞美人の文章についても、主観が入りすぎてはいないか、否、すべて除いてしまうとすべて同じ人物のようになってしまう……と思い悩む場面が書かれる。
だからどうしたといった話ではあるのだが、古代ギリシャ神話とローマ神話に似ている神様がいるよねとか、時間や場所を隔てて似通った記述や描画があると、ワクワクしてしまうのだ。
日々の地平からおりて別の線にのっているとき、フと自分がすっきりするといったそれだけのことであるが、思いがけず出会う、書の外に飛び出していく気づきも、最近の読書のひそかな楽しみになっている。
読んでくださり、ありがとうございます。これを書くにあたって「閃く」のなりたちをしらべたのですが、光はあんまり関係ないのですね〜。


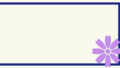
コメント