夏は中島敦を読み直そうと思い立ち、買うだけ買ってだいぶほっといていた。夏がきた。読もう。なぜかといえば、中島がパラオに赴いた経験から書かれた物語の記憶があったからである。そこから「南洋幻想」ということばを友人から教えてもらい、たしかにそういった向きはあるかもしれないなあ、と思う一方で、文学をきわめるにあたっては、寒冷で、どこか宇宙的な深淵さがあり、内へ内へと向かわざるをえないきびしさも魅力的だなと思う。ロシア文学は猛烈に長いし、そんなイメージがある。
さて本編の話。中島敦は享年33、夭折の作家といってよいだろう。岩波版のこちらは11の短編がおさめられており、他にあと少し作品がある。解説にもあるように、ここから世界を広げていこうとしていたのでは、もしそうなっていたらどうだったのだろうといった、前途有望としかいいようのないところで筆は止まってしまった。その儚さも夏のかげろうのようで、夏に読もうのもうひとつの理由だ。
中島敦との出会いは言わずもがな教科書の『山月記』で、そのときに感銘をうけてそのまま、というわけではなく、なんだか時間が経って、働き始めてから「そういえば他の作品ってどんなものがあるのかな」と思いKindleで購入したのだった。その面白いこと!
冒頭の短編『李陵』を読み始め、そうだ、そうだ、この文章のテンポのよさと、すっきりとした切り口である。パキッ、パキッと事実や状況を書き進めていく語り口が小気味いいのだ。あまり読まないけれど、中学時代は井上靖『敦煌』『蒼き狼』あたりがすきで端から読んでいたので、おそらく歴史小説は肌に合うと思っている。
なかでもすきなのが、『牛人』と『名人伝』、そして西遊記の沙悟浄の目線からうだうだとこの世の理を求め、さまよい続ける『悟浄出世』と、同じく沙悟浄の視点から旅の仲間をまなざす『悟浄歎異』だ。前者ふたつは中国の歴史書や思想書を元とした物語で、淡々とした語り口と物語のすすみがいいあんばいにマッチしていてすきだ。とくに『牛人』は一夜の契りを交わした女の情念のようなものも感じられてストーリーっぽさがありおもしろい。『名人伝』はこういうのいいなーと思うような超人伝である。俗世にひたっているかぎりは到底なれない。
悟浄〜の2作は、とにかく沙悟浄が理屈っぽく、なぜ、なぜと知りたがる。この、わからぬうちは動きにくいという臆病さや他者に答えを求めようとするところはまさに「自分だ……」と感じるとともに、その前に読んだ『異常論文』のあとがきにあった「小説は自らの内に」「論文は自らの外に」をここでも感じた。今後しばらく、これは気になっていくし自分のテーマにもなりそうだなーと感じる。中でも、悟空をほめる描写があるのだが、そのみずみずしい筆致も読者の頭に孫悟空その人の躍動感ある動きを想像させる。やや古めの文体ながら見事だ。そういった憧憬をいだきつつも、世の摂理をてんで知らない彼に驚きもしており、旅の仲間たちのバランス感を思わせる。さいご、玄奘三蔵についても少しだけ書かれるのだが、その瞳の見据える世の無情さと、それを受け入れているような諦念とでもいうのか、それがなんだか、万物に対する大きな愛を感じざるをえない。他の話も読んでみたいと思うのが人情だろう。
そういうわけで、数年越しに再読できてよかった。みずからの視点や、染み入る場面の変化もなんとなく感じられ、時の流れを感じるのだった。
読んでくださり、ありがとうございます。今年の後半はむずかしいことが実生活で増えてくるので、北方謙三あたり関心があり、チャレンジしてみようかな。ひとまず、みんぱくの季刊誌がきていて「南方戦線」なので、読み進めようと思います。そのあとでなにか歴史小説を読もうかな。
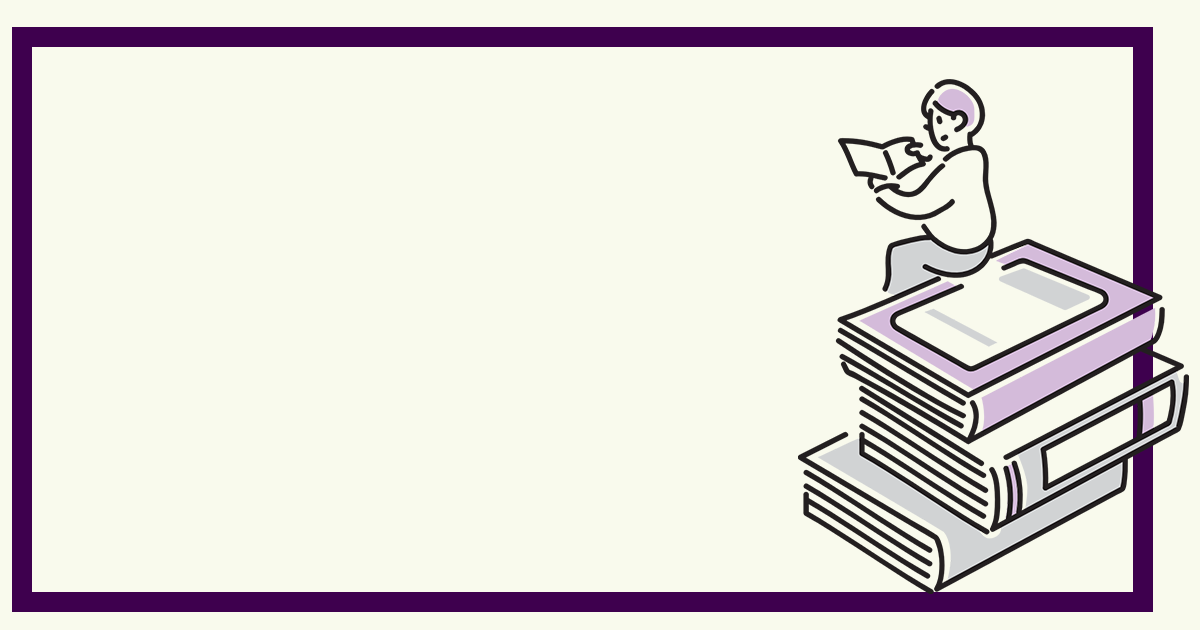

コメント