前書きからして異様な雰囲気がすごい。たくさんの架空の論文が集まってたふしぎな一冊。
テーマもゴリゴリにSFなものから文学の探究をしているものまで幅広く、内容も科学によったもの、文学によったもの、どちらでもあるもの、どちらでもないものがある。とうぜん、あう・あわないや興味の偏りもめちゃくちゃ出るし、あんまり頭に入ってこないなーという作品は読み飛ばしてしまうこともある。まぁたしかに「論文」とあるので、自分があまり関心がなかったり、よく知らなかったりするものが入ってこないのも「それはそうか」と納得いく。基本的にご縁のある本はぜんぶ読み切りたいと思うタイプなのだが、そういうわけなので、読めない・読まないことについてはちょっときらくに構えられた。
内容は割愛するが、巻末で、小説と論文の開く先を考察した解説がとてもおもしろかった。小説の想像力は「自己」へ、論文の想像力は「事実」へ向かうということで、両者のめざす先は逆なのだという。となると、「異常論文」は最初から自己の外部に向けて想像力が発揮されていくのだが、その外部に「自己」も存在するというふしぎな構図になる。筆者が「外部」に広がる「自己」を含めたどのような「要素」に注目するかで作品の読み心地や質も変わるので、本書のバラエティもしかるべきことだ、と解説者は書く。安心した。よかった。
作品のなかだと『SF作家の倒し方』『ザムザの羽』『解説─最後のレナディアン語通訳』がおもしろかった。前者は界隈のおふざけとリスペクトのこもったコミカルな作品、後ふたつはうすぐらい感じで読後感もなんともいいがたい作品であった。たくさんの異常論文を通ったり通らなかったりして、わたしという人間の輪郭にもどってきたような気がした。次の本へ行こう。
読んでくださり、ありがとうございます。やや奇書といってもいい本だったかもしれません。
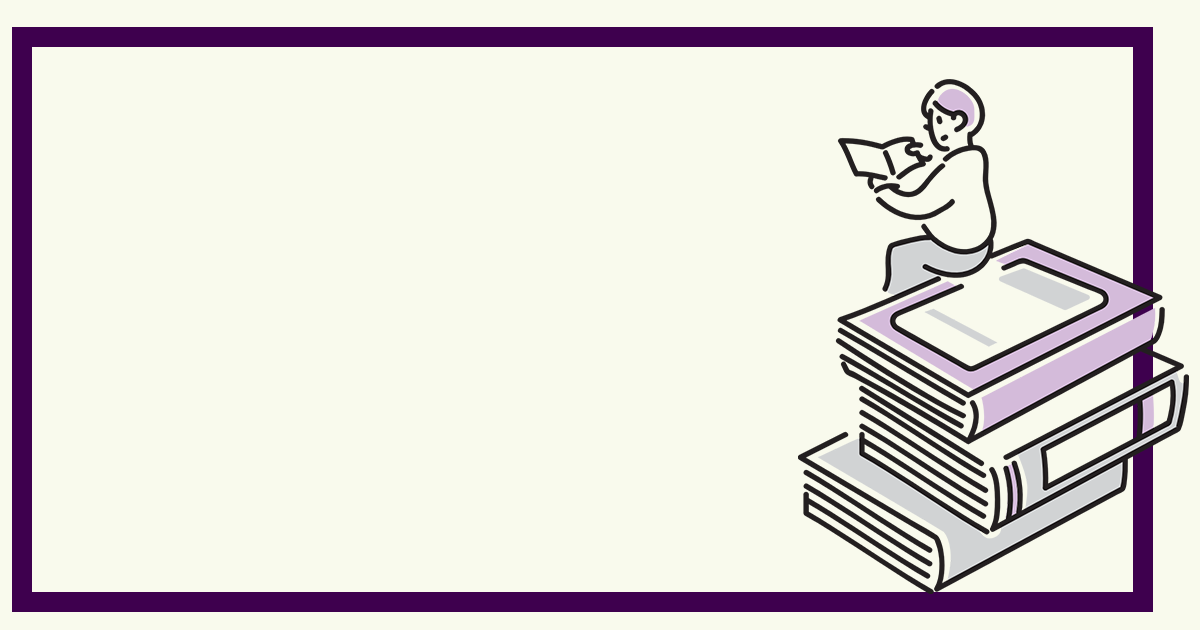

コメント