更新は11月なのだが、読んだのは10月頭で、9月の半ば頃から、ひきつづき田中慎弥さんをせめていった。小さな表現でも「これすごくすきだな」というのが一冊読んでいてもそこここにみられ、宝探しのようでたのしい。
さて、こちらは円城塔さんの『道化師の蝶』と同じ回の芥川賞受賞作品で、先に読んだのが最近のもの(『死神』)なので、どこか飾り気なく、著者の味わいポイントが、どんと表に出てきている感触があった。円城塔さんの作品も前に読んだのだが、テイストが異なっていてコントラストの強さにチカチカした。綿谷りささんと金原ひとみさんのときのような、どこか近しい感じの受賞年ではなかったことがよくわかる(感じ方には個人差がある)。
「共喰い」、とてもよかった。鬱屈としたところからのカタルシスとでもいうのか、カタルシスとしていいのか。どうしようのもない現実に対するささやかな抵抗をつよく感じた。もんだいが解決したわけではないけれど、おはなしの展開としては、少し霧がはれる。ただ、そこに生きる救いがあったのか、その先主人公がのぞむように生きていけるのかは、また別のことがらだな、と思わされるおわりだった。
「第三紀層の魚」のほうは、湯本香津美さんの『夏の庭』をはじめとして、死にそうな老人と小学生の話が昔からなんかすきなんだよな。小学生ではないが、羽田圭介の『スクラップアンドビルド』もすきだ。対比なのか、生きることじたいなのか、なんだろうな。主人公と曽祖父とのやりとりはとてもよくて、その変化の過程もじわじわと切迫していく。数年前、自分の祖母が認知症になり、記憶から自身が忘れ去れたり、小学生のときかな、祖父のときに死にかけの状態をみて「あ、死ぬんだな」と思ったことなど、自分の体験を想起しながら主人公の立場で祖父の傍に立つような感覚もあり、全くこの主人公とは家族関係が異なるのだが、へんななつかしさがあった。
本編のあと、瀬戸内寂聴さんとの対談があるのだが、そこにも、創作することで現実と自己との間に壁をつくれる、というのも、同じようになんだかいいし、特段今は何も作っていないが、わからなくないな、と思わされた。しごとをすることを通して、高校・大学の頃よりは骨太になったかな、と思わなくはないが、他方、日々に忙殺されることで目を背けている自身の根本的な弱さや厭世的な気持ちにも蓋をしながら生きているなーと思わされた。強く骨太になることばかりがいいことでもないような気がして、なんだかそういったところにもきちんと向き合いながら言語化していけたほうが、抜本的な解決に至るような……。
一旦、ここで田中慎弥さんの作品は読み終えて、別の作家さんにうつろうと思うのだが、インタビュー等でもよく言及されておられる「死にたいと思っていたり絶望していたりする人でも、その間に本を読む。その間は生きていられる、死なずに済む。」(うろ覚え)という話がとてもすきで、今、すすんで死にたいわけではないけれど、1日の中で本を読める時間は短いけれど重い。別の世界に飛び込み、「他にも知りたい読みたい」と、生きていないとできないことに心が向いてくれるので、死ぬことを考えなくてよい時間がふえる。
読んでくださり、ありがとうございます。こういうふうな方が自分っぽいなと感じます。しごとは人格の改変をしていかないとやってけないってことです。
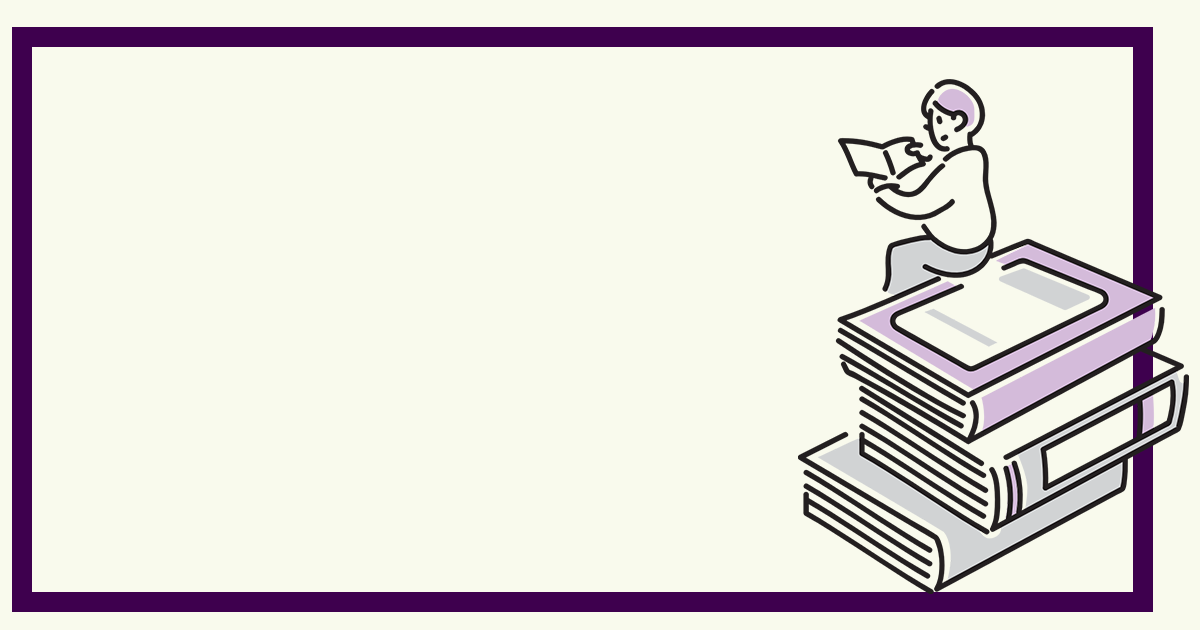


コメント