物語では幕引きとなる死も、現実の世界では綺麗なピリオドにならないことは多い。残された者、物、金、それらを取り巻く手続き。世の仕組みとして必要ではあるのはわかる。わかるのだが、だからといって、つねに死ぬことを考えて生きているわけにもいかない。そういう意味では「手続きを見守る者」として伴走する姿が、士業的なしごとのなかに見出せるかもしれない。
命の重みは同じだが、戦乱の中で失われるのより、日本は比較的緩慢に失われていくことのほうが多い……気がする。だからこそ煩雑な手続きのいろいろを引き受け、連なる場面もみられるのかもしれない。そうして死に向かい、その多くは衰弱していくこと、一般の老いに対する声は、平時あまり聞く機会がない。『夏の庭』(湯本香樹実)の主人公である小学生たちが、近所の老人の死に関心を持って近づくような不謹慎さはあれど、未知の領域であることは確かであるし、たしかに聞いてみたいと思う。人の寿命がのびていく中、遅延させる技術は増えてきているが、今のところ知る限りでは、誰もに訪れることだ。にもかかわらず、直視するのは老いたそのときという点であり、その過程には目を向けづらい。それを見たい。なぜか。知らないことであり、知っていく過程で、死や老い以外のことも見えてくるような気がするからだ。あとは実用的な面で、どこに引っ越したとしても人は死ぬので、こちらにいるうちにやっておきたい。
字義通り捉えると死神のような立ち位置であるが、命をとるわけでもなし、それどころか、傍で手続きを見守ったり、代行したりと、なんだか味方っぽい感じもある。相続や後見においては、たびたびそんなポジションになるのかなと、実際の相談の場面をみていても感じるところではある。ときにまきこまれることもあるのかもしれないが、福祉的支援の臨床とも似ているようにみえた。自分でやってみるまで判断しがたいが、準備ができたところで、知らない世界に潜っていこう。できればもうすぐとびこめるようにはしたいのだが……。
読んでくださり、ありがとうございます。しごとを知っていけばいくほど、士業のしごとは栞のようだと思います。
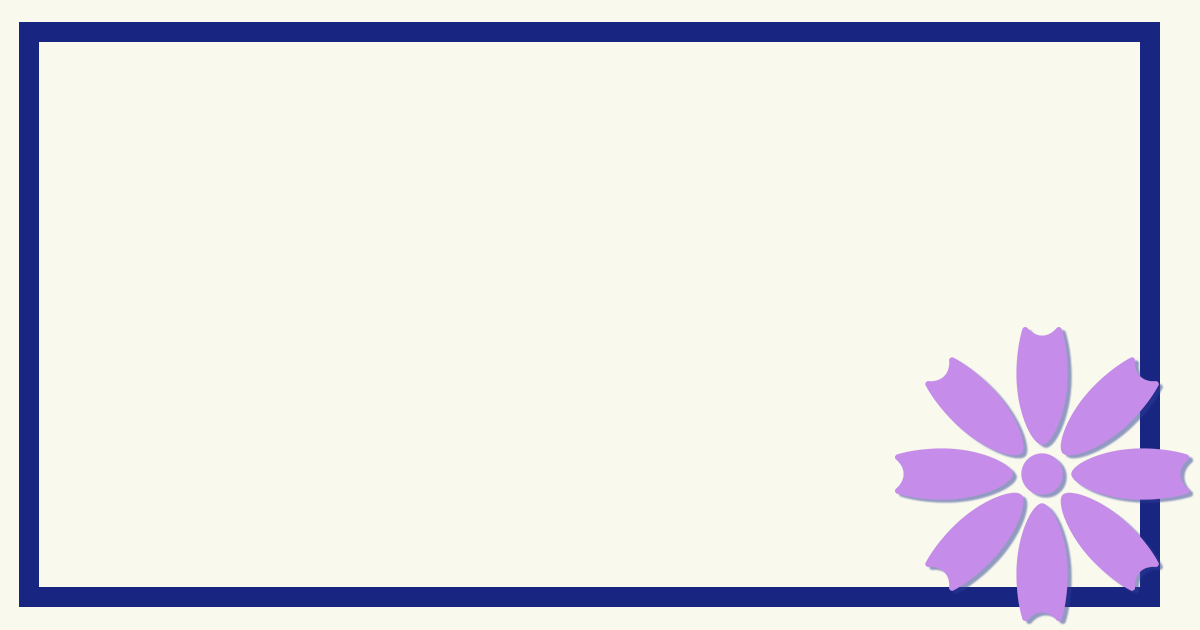


コメント