イラクの中にあるアフワールという、イランとトルコに近い湿地帯の人々の暮らしを追ったドキュメンタリー。著者の高野秀行さんは、10 年弱くらい前だろうか、『世界の辺境とハードボイルド室町時代』という、歴史学者の清水克行さんとの共著で出会った。このときはソマリアだったのかな、それと室町時代のカオスぶりが、対談を通して、だいぶ一致しているところがある!といった気づきを書いている本で、現代世界と歴史とのエキサイティングな交差を見せつけられたのを覚えている。そんな、高野さんのチャレンジングな一冊である。
コロナ禍も重なりなかなか思った通りにいかない旅程ではあるが、その予定外・急場のできごとも含めてぜんぶがおもしろいし、これがあったからこそ今回の本が出来上がっているのだと思うと、感慨深くもある。
一冊を通して、アフワールの今をていねいに描写しており、現地の人柄とくらし、湿地帯のくらし、船旅にむけて、コロナ禍国内で出会った謎の布と、どのテーマもおもしろいのだが、特に印象に残ったのは、シュメール人にたびたび言及していることである。シュメール人は紀元前のメソポタミア文明の中でさーっと触れられる程度の記述なのだが、高い文明をつくっていながらも、忽然と歴史から姿を消すといったミステリアスさがあり、開発したといわれた線文字がいまだに解読しきれていないことや、「目がめちゃくちゃでかい」といった謎の説もあり、なんだか気になっちゃう人々なのである。それがアフワールの湿地の旅の中でたびたび出てくることに興奮をかくしきれず、ものすごいいきおいで読み進めてしまった。冷静に考えるとメソポタミアの土地にいた人々なのでふしぎではないのだが、話の舞台は現代イラクである。シュメール人という文字をみるとは思いもよらず、ますます惹かれてしまうのであった。
本編である旅の方も、本家『水滸伝』リスペクトで、現地の人々を登場人物になぞらえ、一緒に旅をしていく。読んでいるとだいぶ面白おかしく書かれており、実際に楽しんでおられたと思うのだが、想像以上にマイペースであったり、行動様式の異なる現地の人々や、コアとなる人物の体調不良によって思った通りに進まない旅路には、やきもきさせられたことと思う。とはいえ、その場その場の状況に応じて柔軟に旅を進めていく著者らには、旅慣れの気概と、本書でも何度か言及される「ブリコラージュ」(エンジニアリングの対語。その場にあるリソースで必要なものを作ってまかなっていく姿勢)が、旅全体ともくっきり重なっているように思われ、構成としても美しい一冊である。
読んでくださり、ありがとうございます。高野さんの著作からしか得られないエッセンスを改めて感じたので、ちょこちょこ挟んでいきたいと思いました。フィクションでもノンフィクションでも、そういう作者さんいますよね。
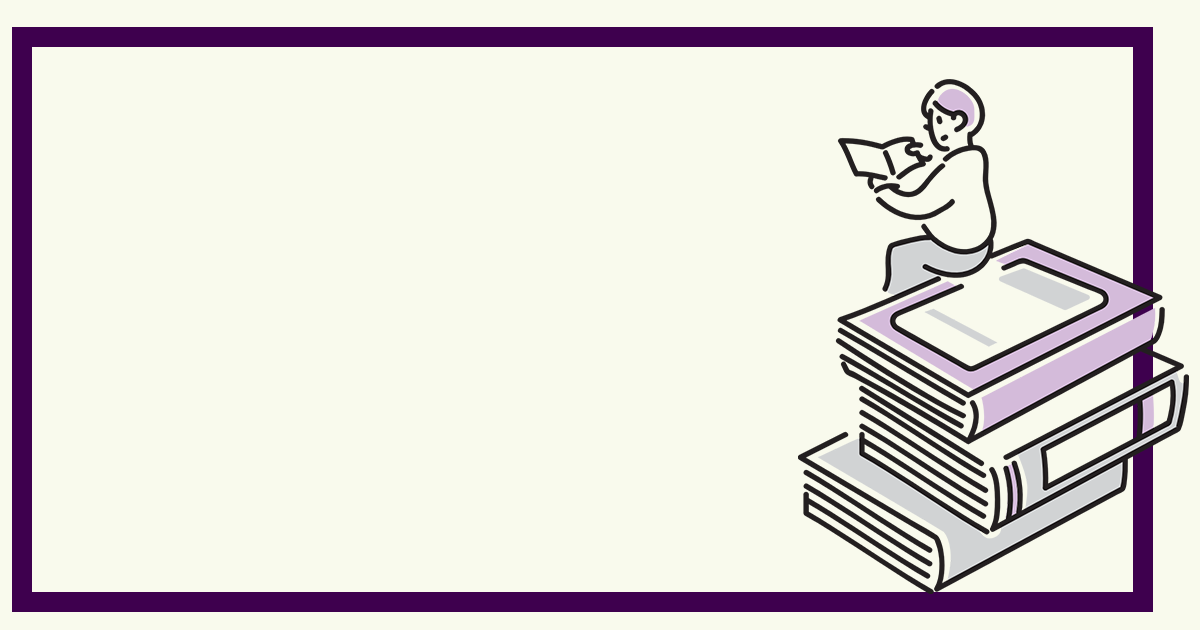


コメント